Posts Tagged ‘曳山の説明’
西行桜狸山(鍛冶屋町)

音声案内 西行桜狸山は、大津祭の元祖となった曳山である。慶長年間(1596-1615)に鍛冶野町の塩売治兵衛が、旧暦九月十日の四宮祭礼に、狸の面をかぶって采を振って風流踊を踊ったのに始まる。続いて治兵衛を乗せた屋台を担い [...]
猩々山(南保町)

猩々山の概要 この山は、能楽の「猩々」に因んだものである。すなわち「昔中国の揚子の里にコウフウー高風という人がおり、親孝行であった徳により夢の中に奇瑞があらわれた。それはコウフウが揚子の街に出て酒を売れば必ず富貴な身分に [...]
西王母山(丸屋町)

西王母山(桃山)の概要 西王母山は丸屋町から出る山で、普通に「桃山」ともいっている。大津市役所の調査資料によればその製作年代は明暦二年(1656年)と古いが、現在のものはその後の何回かの改造や新造部分が多く、建築関係では [...]
西宮蛭子山(白玉町)

この山は恵美須山(えびすやま)あるいは鯛釣山(たいつりやま)といい、市役所の資料によれば最初は宇治橋姫山と言ったとのことである。そして明暦二年(1856年)にでき、のち延宝年中に西宮恵美須山にかわった。古くから毎年えびす [...]
殺生石山(柳町)

殺生石山の概要 殺生石山は玄翁山とも言い、大津市教育委員会発表の資料(昭和40年)によれば、延宝元年(1673年)、一説に寛文二年(1662年)に造られたという。この山の由来については同資料に「能楽・殺生石を取り入れたも [...]
湯立山(玉屋町)

湯立山の概要 大津市教育委員会、社会教育課の調書(昭和40年)によれば、湯立山の創始は曳山中最古で寛永3年(1826年)と伝えるという。天孫神社の祭事に湯を奉献する行事があり、その湯はこの山から捧げ、この湯をかけられた [...]
郭巨山(後在家町・下小唐崎町)

由 緒 町有文書「四宮祭礼牽山代記」によると 一、元禄六葵酉年 郭巨山 橋本町 一、享保十五庚戌年 橋本町牽山天井綺麗に替る。 一、明治十九年 橋本町から鍛冶屋町に譲渡されたが、明治二五年後在家町などに譲られ現在に至 [...]
孔明祈水山(中堀町)

孔明祈水山は孔明山と通称する山で、大津市役所資料によれば最初福聚山と言い、元禄七年(1694年)にできたが、万延元年(1860年)、孔明祈水山と名を変えたという。その由来については、蜀(中国三国志参照)の諸葛孔明が魏の曹 [...]
石橋山(湊町)

石橋山の概要 石橋山は唐獅子山とも言い、大津市役所の調査資料によれば江戸初期、寛永二年(1625年)または正保二年(1645年)の製作と伝えるという。山の名は能楽「石橋 しゃっきょう」に因むもので、その由来は天台宗の僧の [...]
龍門滝山(太間町)
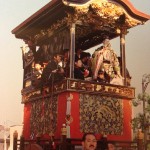
龍門滝山の概要 鯉山は別名を竜門滝山ともいう。向唐破風をもつ三輪の曳山で、製作年代は享保二年(1717)というが、多くの部分は江戸末期乃至それ以後に造り替えられている。主体構造は下層の車台、その上の下層(1階)櫓、これよ [...]
神功皇后山(猟師町)
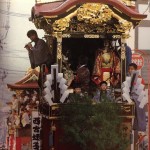
神功皇后山の概要 大津市教育委員会発表の資料(昭和40年)によれば、この山の由来は「神功皇后が三韓へ行かれる前に、今の長崎県北松浦在の鮎釣り岩で真直な釣針で鮎を釣り上げた時の説話に基く」としており、又この時皇后は懐妊中 [...]
月宮殿山(上京町)

月宮殿山の概要 月宮殿山、鶴亀山とも呼ばれるこの山は能楽「鶴亀」に因んで名付けられたという。これについては『日本百科大辞典七』(大正5年3月三省堂)によれば「唐土の皇帝不老門に出御あり、壮厳華麗を極めたる庭上に青陽(春の [...]
源氏山(中京町)

大津市歴史博物館発行 「町人文化の華ー大津祭」大津祭りの発生とその展開 木村至宏氏 を転記 大津祭は、本市の中央部に位置する京町三丁目の天孫(四宮)神社の祭礼である。かつての社名から四宮祭ともよばれていた。そして長浜曳山 [...]








