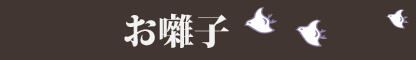 |
 |
| 源氏 | 源氏山の囃子の中でも基本的曲目。巡行の午前中は天孫神社から巡行開始するので囃子方も紋付き姿という儀礼的格式を持った姿で演奏を行う。 | |
| 千鳥 | 「流し」と曲はほとんど一緒だがゆっくりと演奏する。また曲と曲の間に挟み込む「渡し」というがある。曲を変えるとき次の曲名をリズムに合わせ「ちどりーやーちどり」等と掛け声を入れ、太鼓のソーレで「渡し」に入り「渡し」終了後、掛け声を入れた曲を演奏する。巡行中の曲順は状況に応じた柔軟な対応が可能となっている。 | |
| 所望 | 所望というのは、山に仕掛けてあるからくり人形を動かすことで、からくりの動きに合わせて演奏される。太鼓と笛のみで、子供たちはからくりを動かしている。 | |
| 唐子 | 天孫神社の鳥居の前で所望(しょもう)を奉納した後に演奏する曲で、2回繰り返す。この曲はこの場所だけ。ほかでは演奏しない。 | |
| 乱れ | 巡行中の囃子に変化を求めて、合間に入れる曲。どの囃子もパートの繰り返しだがこの曲だけ鉦、太鼓、笛の繰り返す位置が違っておりこの曲名がついている。 | |
| 流し | この曲は坂をあがるときに演奏する曲で、平坦地ではゆっくりだが、坂に応じて曲のスピ−ドを増す。千鳥と笛は同じ。太鼓に変化があり又力量が問われる曲。 | |
| 宵山 | 山の巡行の前夜、宵山の晩に行う華やかな曲。各町で共通した数少ない曲であり、他町との合同演奏が可能である。 | |
| 戻り山 きおい | 正式な祭りとしての巡行が完了し、自町へ戻るときに演奏する曲。15秒位が1クールの繰り返しで単調ではあるが、演奏している側は1時間やっても飽きない不思議な魅力を持つ曲。 | |
囃子方 昭和62年11月1日 京都太秦 井進録音スタジオ |
||
 源氏山の囃子しは概ね他町と同じであるが、同じ曲名でも曲が異なったり、また、同じ囃子でも曲名の違うものもある。その上、同じ曲目でも若干調子が変化しているものもある。とくに鉦・太鼓に合奏する笛にその傾向か多くみられる。
大津祭総合調査報告書「源氏山」中谷広次氏 発行所 滋賀民族学会 より抜粋
|