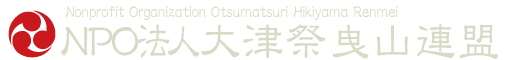湯立山の概要
大津市教育委員会、社会教育課の調書(昭和40年)によれば、湯立山の創始は曳山中最古で寛永3年(1626年)と伝えるという。天孫神社の祭事に湯を奉献する行事があり、その湯はこの山から捧げ、この湯をかけられた人は五穀豊穣、悪疫退散、商売繁昌すると縁起を祝う。現在の湯立山は建築・工芸方面では江戸初期や同中期に溯るものがなく、江戸末期およびその後の製作に係るものと認められる。
構 造 形 式
他の曳山と同じく上・下層に大別できる三車輪をもつもので、主体構造、軸組は他の山と同型である。下層は四方に高欄付の縁をめぐらし、その内側左右は菱格子欄間をもつ透塀型、前後は蔀(しとみ)格子型の繊細なものを飾る。これ等は天孫神社の建築に型取るという。
上層は型の如く内転(うちころ)びの四本柱「漆塗、要処に熨斗目飾(のしめかざり)を極彩色で盛り上げ〕を立て、斗栱三ツ斗、屋根は妻を正面とする入母屋、柿葦(こけらぶき)を模する。斗栱間(ときょうま) 〔頭貫(かしらぬき)上」には青竜・白虎・朱雀・玄武の四神彫刻を飾る。天井は格天井、軒は一軒、二本ずつの吹寄垂木(ふきよせだるき)である。妻飾り狐格子(きつねごうし)、懸魚(げぎょ)は鰭(ひれ)付のかぶら懸魚(かぶらげぎょ)、棟端は下層の透塀と共に獅子口。
大体以上のようなものであるが、これ等の各部材のもつ様式は江戸末期様式で、寛永まではとても溯れない。その時期は未確定であるが、この山を納める土蔵の棟木に「文致十三年......」 (1830年)の墨書があり、現在の湯立山の造立年代の参考とすることができる。結局建築・工芸方面では京都の祇園祭の山や鉾などとおよそ近い頃のものと言えそうであるが、彫刻・漆工・画工・金工等の方面で当時の最高作を目指した優秀作品が揃っている点を第一に見るべきであろう。
近藤豊 記「大津祭総合調査報告書(3)湯立山 滋賀民族学会発行 1972年発行」より抜粋
人 形
二層の上手、右手に御幣をもつ称宜人形が立ち、中央奥に巫女市殿が両手に笹葉をもち、下手に飛矢が両手に鉦をもって立っている。三体とも等身大の大人形である。
所 望
大太鼓と笛の囃子で称宜が、まずお祓いをする。巫女が笹葉を上下に振って前にある釜の湯を立てる身振り、飛矢が鉦を打って、首を左右に振って神楽を舞う。これは天孫神社に湯を奉る神楽舞を納める振舞である。
由 緒
口伝えによると寛永三年に創建、大津山中の最古の山といわれている。四宮祭礼牽山旧記の古記録中では第七番目に数えられているが、これは寛文年中に孟宗山から湯立山に替ったためで、孟宗山は寛永三年に初まった故に最古と言うのであろう。
「元禄六年牽山練物くぢ取濫觴左之通」の内にも「湯立山玉屋町」とある。また享保二十乙卯年玉屋町 廻廊幕押見事出来」の記録がある。湯立山の巫女人形の飾台に「寛文四年辛未調之」と大きく墨で書かれている。この年号と干支とが一致していない。寛文四年に最も近い前後の干支を求めると寛永八年辛未(1631年)と元禄四年辛未(1891年)になる。この年号干支不一致の詮索は別として愚考するに、寛文四年が湯立山に替った年で、辛未は孟宗山が創建されたことに関係深い年ではないのだろうか。しかも書き込まれたのは二・三十年後のことではないだろうか。年号干支の不一致は湯立山に限ったことではない。湯立山以外の地でも古い時代のもの程、稀ではあるが散見できる。従って筆者は不一致を度外視して四宮牽山旧記を重視してゆきたい。
そこで、祇園会十七日山鉾の図に烏丸四条上ル町から孟宗山が曳き出されている。大津の孟宗山と無関係ではないであろう。これが明暦二年(1656年)に湯立の神事をかたどる湯立山に替ったが、湯立は山車の中でもからくり戯を除いたものの中では最も多い演目に属している。他の地方での二番目の山車では名古屋の桑名町の万治元年(1658年)に新造された湯取神子車がある。人形は小細工師二郎ハ(人形師)の作で白幣を持つ祢宜(ねぎ)をおき、前面に忌竹を立て、注連をはり、中央に湯立の釜をおいている。巫女が両手に笹葉を手に持って湯立の神事を司るあやつりである。元禄時代の絵草紙では前面に釜が一米半もつき出している。元文時代には巫子が湯立をする時、紙片を釜から湯花のように吹き散らす工夫もあったという。天保五年(1834年)に筒井町四丁目に譲渡された侭、今日に至っているが、幾度も修理され、昔日を偲ぶ古態はなくなっている。その他では小伝馬町の湯取車(年代不詳)、小牧市の上の町の湯取車、津島市麸屋町の湯立神子車(享保期)、同市朝日町の湯取神子車(天明記)、最後に羽島市竹鼻町大西町の場取神子(天保期)、すべて操りで人形を使う。
湯立の山車はからくりではなくあやつりで操うものが多い。この湯立の名は名古屋での時代の順位からいえば、第四番目に位し、山車に屋根をつけたのがこの湯立から初まっている。湯立の山は京都にはなくなった。従って記録の上では万治元年創建の名古屋の桑名町の湯取神子は最古の湯立山車である。これが天保期に筒井町に購入された。この人形操法を見ると文化期以降の操法に変って樋が登場している。また享保期の津島の綾りは宝暦期のからくりとあやつり操法にかわっている。大津のように、あやつり前期の操法は他所では全く見られない。このことが重要なのである。
山崎構成 記「大津祭り総合調査報告書(3)湯立山 滋賀民族学会発行 1972年発行」より抜粋
より大きな地図で 大津祭 宵宮の地図 を表示